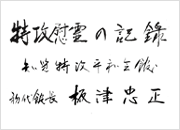人が変わる修学旅行生たち
<板津>今、知覧特攻平和会館の入場者は年間72万人を超え、増加の傾向にあるんです。修学旅行生もたくさん来てるんですよ、年間5百校以上。バスから降りた生徒さんたちはガヤガヤしながら物見遊山のつもりで入っても、出るときは人が変わったように「先生、時間がほしい!」「もう一度必ず来ます!」という生徒もいて、住民たちもびっくりするほどの変わり様です。引率の先生方の中には「全国の中学生がここにくるようになれば、暴力教室も家庭内暴力もなくなるだろう」といわれる方もいます。
<聞き手> 真実の持つ重みですね。
<板津> 例えば小学生の子どもたちがくると、次のようなカタカナ書の遺書を目にするわけです。五歳と二歳の二人のお子さんがおられた愛知県の久野正信大尉は、全文カタカナの遺書を書かれました。片仮名だと小学高低学年で習います。一日も早く、父親の心情を伝えたいとの親心でしたのでしょう。
正憲、紀代子へ。父ハスガタコソミエザルモ、イツデモオマエタチヲミテイル。ヨクオカアサンノイヒツケヲマモッテ、オカアサンニシンパイヲカケナイヨウニシナサイ。ソシテオオキクナッタレバヂブンノスキナミチニススミ、リッパナニッポンジンニナルコトデス。ヒトノオトウサンヲウラヤンデハイケマセンヨ。「サマノリ」「キヨコ」ノオトウサンハカミサマニナッテヂットミテヰマス。フタリナカヨクベンキョウシテ、オカアサンノシゴトヲテツダイナサイ。オトウサンハ「マサノリ」「キヨコ」ノオウマニハナレマセンデシタケレドモ、フタリナカヨクシナサイヨ。云々。(>二人の子どもたちに宛てたカタカナの遺書)
これを見て現代の子どもたちも子どもながらに感動するんですね。また義母への思いをつづった絶筆集には、
母上、お元気ですか。長い間、本当にありがとうございました。我六歳のときより育ててくだされた母。継母とはいえ、この種の女にあるがごとき不祥事は一度たりとなく、慈しみ育てて下されし母。ありがたい母、貴い母、おれは幸福だった。ついに最後まで、「お母さん」と呼ばざりし俺。幾度か呼ぼうとしたが、何と意思薄弱な俺だったろう。母上、お許しください。さぞさびしかったでしょう。今こそ大声で呼ばさせていただきます、お母さん、お母さん、お母さんと。
<聞き手> 修学旅行が五百校も来るということは現代の教育のおかれた状況の中で一筋の光明をみる思いがします。
<板津> やはり教育ですね。特攻隊員の美しい心根も教育の賜物であれば、今日の日本も戦後の教育の賜物です。会館がオープンした当初は、修学旅行などは一校も来ませんでした。日教組とかの先生方の偏見だったのでしょうか。あるとき、教育関係者の全国大会があって、校長会やPTAの会長さん方数百名を前にして話をする機会がありました。ここで平和教育の殿堂としてふさわしいとの批評をうけ、徐々に修学旅行が増えていきました。先生方も自分たちの平和教育の在り方を反省する契機となっているようです。ことに高校生ともなれば、自分と同じ年代で逝った少年たちもいるわけで、彼らの達筆さにまず驚く。そして国のために家族のために自らの全てを犠牲にして飛び立ったその純真な思いは歳月を飛び越えて直に訴えてくるのですね。
靖國に一緒に入ろうとの誓い
<聞き手> 特攻平和会館建設に賭けられた思いをお伺いさせてください。
<板津> 戦後、長い間、知覧は無名で、特攻基地があったことや特攻観音は、あまり知られていなかった。特攻を観光に利用しては申し訳ないという気持ちが知覧の人々にあったからです。しかし私は、これは歴史上の事実だから、その真実は後世に伝え残すべきだと主張したのです。

<聞き手> 板津さんはなぜ特攻を志願したのですか。
<板津>国のため肉親のために散る一念でした。この写真は、私の部隊が出撃するとき水盃を交わす場面で、中央の一番小さいのが私です。これで一人前になった、お国のため家族のためになるんだという満足感がありました。私は20歳でしたが、当時の仲間は皆そうだったんですよ。私らは特攻にいくときに靖國神社に当然入るものだと思って「それぞれに出撃してあちこちで体当たりしても、最後は靖國神社の鳥居のところに集まって一緒に入ろう」と言い交わしていました。ただ自分たちが死んだあと、日本がどのようになっていくのか、そのことだけが心残りでした。そのため、私は、靖國神社に参拝するときはいつも「今、日本はこうなっています」と報告しています。でも、最近は非常に心苦しい時がある。こういう時代になってきたからね。今日の世相を靖國の御霊にどう報告すればいいのか、つらい気持ちがします。
靖國に一緒に入ろうとの誓い
<聞き手> 特攻平和会館建設に賭けられた思いをお伺いさせてください。
<板津> 戦後、長い間、知覧は無名で、特攻基地があったことや特攻観音は、あまり知られていなかった。特攻を観光に利用しては申し訳ないという気持ちが知覧の人々にあったからです。しかし私は、これは歴史上の事実だから、その真実は後世に伝え残すべきだと主張したのです。
<聞き手> 板津さんはなぜ特攻を志願したのですか。
<板津>写真あり
国のため肉親のために散る一念でした。この写真は、私の部隊が出撃するとき水盃を交わす場面で、中央の一番小さいのが私です。これで一人前になった、お国のため家族のためになるんだという満足感がありました。私は20歳でしたが、当時の仲間は皆そうだったんですよ。私らは特攻にいくときに靖國神社に当然入るものだと思って「それぞれに出撃してあちこちで体当たりしても、最後は靖國神社の鳥居のところに集まって一緒に入ろう」と言い交わしていました。ただ自分たちが死んだあと、日本がどのようになっていくのか、そのことだけが心残りでした。そのため、私は、靖國神社に参拝するときはいつも「今、日本はこうなっています」と報告しています。でも、最近は非常に心苦しい時がある。こういう時代になってきたからね。今日の世相を靖國の御霊にどう報告すればいいのか、つらい気持ちがします。
生き残った者の務め 遺族を訪ねて全国行脚
<聞き手> 知覧に戻られてからは。
<板津> 三角兵舎の人となり、生きていることがこれほどつらいと思ったことはなかった。早く出撃命令をくれと嘆願して漸く命令を受領して、明日はいよいよ皆のあとを追うことができると喜んだのもつかの間、その日が来ると土砂降り。今振り返っても昭和20年の梅雨ほど降った年はなかったのではないか。

六月下旬、沖縄陥落と同時に特攻作戦は中止となって、私は本土決戦要員のため知覧に留まり、終戦、復員しました。死が当然であった特攻隊員が生きていることの精神の呵責がどれほどのものであるかは体験したものでないとわからない。あのとき故障さえなければの悔恨はその後夢の中にまで現れた。その慙愧に堪えない思いで生き残った自分の務めとしてせめて自分の隊だけは何か残してやらねばと終戦後二ヶ月間、ご遺族を捜し歩きました。
その後、郷里の名古屋市役所に就職しましたが、隊員たちのご遺族は、わが子兄弟がどこから飛ぶ立ってどこへ突入したか、死亡報告書だけは知る由もなかった。このままでいいのだろうか疑問にもち、いつか機会を見て少しでもお報せしようと思っていました。
そして昭和48年から49年、かつて復員局業務部が作成した特攻隊戦没者芳名簿を入手しました。これを手にしてから私は手紙を書きまくった。1年に360通ぐらい。戻ってきたのも多かった。 返事をくださった方には、用意した知覧、万世の写真を送り、文通が始まって、心が通じるようになって、貴重な遺書、遺影、絶筆を送ってくださる方も出てくるようになりました。当初は、仕事を抱えながらでした。土日を利用して近隣を回り段々と範囲を拡げていった。ご遺族に直接お会いして当時の模様を伝え、遺影はカメラに収め、遺書、絶筆、遺品等はコピーしたり提供をうけたりしました。しかしやがてこれでは追いつかんと思い、定年を待たずに勤務先を辞め、全国行脚に集中しました。一日も早く収集しなければ資料は散逸してしまう。彼らの跡を残さればならない一心でした。全部自弁で車で回り、3年十万キロ、40日間で六千キロ走ったこともあります。
<聞き手>大変な作業ですね。
<板津>実は、入手した名簿は誤りだらけでした。だから地元の古老に聞いて回るしかなかった「ここらあたりにパイロットはいませんでしたか」と訪ねて歩いた。ですから一人見つけた時はすごく嬉しかったですね。
<聞き手>ご遺族の反応は。
<板津> 初めは不安でした。「今ごろ何しに来た」と言われるような気がしてね。実際は、「よう来てくれた」とほとんどのご遺族が我が子が帰ってきたかのように歓迎してくれました。生きておったらこんなふうかと亡き人と重ね合わせてみていたのかもしれません。少しでも我が子兄弟のことを教えてくれという気持ちがひしひしと伝わってきました。
当時の隊員の様子について一つだけお話しますと、南九州を旅してバスに乗るとガイドさんがホタルになった兵隊さんの話をします。新潟県出身の宮川三郎軍曹(後、二階級特進)のことです。この話が有名になって映画「ホタル」の題名となったのです。
彼は小学校時代、学級長でしたが、副級長に松崎義勝という人がいた。二人はライバルでした。先に松崎が少年飛行兵に志願した。宮川は負けたと思って後、民間パイロット養成所に入所した。私と同期生でした。二人が別れてから丸4年経った昭和20年5月末、二人とも特攻隊員として知覧でバッタリ再会。語り明かした翌日に松崎は出撃して行った。「今度も俺が負けた。」俺は何と運が悪い男か」。実は、宮川は4月に第14振武隊隊員として出撃したが、エンジン不調で帰還していたのです。それでまたしても副級長に先を越されたと悔しがった。そのとき二度と帰ってくるものかと心に期した。その気持ちは私にはいたいほどわかるんです。そして宮川は6月6日満20歳の誕生日の翌日に滝本という隊員と一緒に出撃した。しかし今度も悪天候。滝本が戻ろうと懸命に促すけれども、宮川はお前だけ戻れ、俺は絶対戻らないといって飛んで行ってしまった。帰還した滝本は、終戦後復員したが重圧に耐えかねたか3年後に亡くなった。宮川三郎だけがホタルになった兵隊さんとして永久にその名が残ることになりました。
宮川の郷里の新潟の小千谷(おぢや)の一本杉は蛍が飛び交うところ。その光景が脳裏に浮かんだのでしょう。しかし知覧では、通常ホタルは七月以降にしか出ない。故に余計に彼が出撃した日に富屋食堂に出現したそのホタルは、宮川三郎の化身であろうと信じられたんですね。
遺族探しの旅の過程で、私は亡くなった御霊が見守ってくださっているという気がしました。不思議な遭遇もよくありました。例えば、どうしても探し出せなかったご遺族の方とカナダの旅先で出会ったり、別々のつてでお願いしてあった遺影が5年もたった全く同じ日に双方から郵送されてきたり。
<聞き手> そうした積み重ねが遺品館、現在の特攻平和会館に結実したわけですね。
<板津> 全国行脚も一通り終えたところで初代の館長に迎えられて、4年間務めました。そのままそこに骨を埋めるつもりでした。ところが開館当時、まだ三百八十四名分の遺影が空白だったんです。館内案内で説明していると、空白の隊員が早く家族を探してくれと私に訴えるわけなんです。また一緒に出撃した隊は固まって展示してありますから、早くここを埋めてくれないと俺たち寂しいじゃないか、お前がやらなくて誰がやるんだと叱られてるような気がして、いたたまれなかった。それで私はもう一度全国を回ろうと決意したんです。そして平成7年ようやく千三十六名の全員分がそろいました。
特攻小母さんたちへの恩返し
<聞き手>トメさんの思い出をお聞かせください。
<板津>トメさんは、戦時中は他の隊員たちと同様、子どものようにかわいがってくれました。後で聞いたところでは、当時トメさんは着物を質に入れてまで隊員たちをもてなしたという。憲兵ににらまれてまでも隊員たちに愛情を注いでくれた。
私にとって戦後は精神的支えでした。「あんたが生き残ったんは、特攻隊のことを語り残す使命があったからじゃないの」と激励してくれました。資料集めの間も常に特攻おばさんのことは念頭にありました。おばさんが生きているうちに全部集めると心に期していましたがそれは叶わなかった。 隊員たちはほとんどが知覧には一泊か二泊、せいぜい三泊の滞在だった。その短い間に隊員たちがトメさんはじめ知覧の人々から受けた厚情は計り知れない。ことに死ぬ直前ですからその親切は心に染み入るものでした。そのご恩返しは誰がやる?生き残った私がやるしかないじゃないか。そんな思いも私の背中を後押ししていました。
<聞き手> 板津さんの残された仕事がもしなかったならば、ご遺族も永久に亡き人の最後の様子を知ることはなかったのかもしれないし、今日私たちがこうして歴史の真実に触れることもなかったかもしれません。
<板津>多くの資料も埋もれたままでいた可能性はありますね。知覧の町長さんがほめてくれたり、会館を多くの修学旅行生たちが訪れてくれたり、あるいは大学生が卒論のテーマにしたいと訪ねてきたりする様子に、私も生き残りの恥に耐えて生きてきた甲斐はあったかなあと思わないでもないんですが、しかしそれでもやはり生き残った負い目は背負い続けていかねばなりませんが、その間は、体力、気力の続く限り特攻隊の真実を語り継いでいきたいと思います。
2002年(平成14年)7月インタビュー